一般酒類小売業免許と通信販売種類小売業販売免許が必要な場合とは
酒屋でビールを売るのと、飲食店でビールを出すのと違うの?といったお話です。
酒屋をやりたい。ネット時代なんだから通販でやれるんじゃないか?なんて方向けの初歩の初歩の基礎知識です。
また飲食店の方が意図せず違法にならないために注意した方がいいこと等もありますのでご覧ください。
提供と販売
提供
さてさて、飲食店で
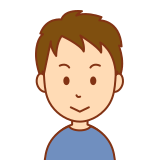
瓶ビールお願いしまーす。
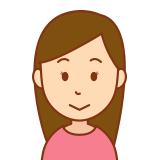
はーい。ただいまー
といった状態ですね。
これには、基本的に酒類販売免許は不要です。あくまで提供だからといった考え方です。
ただし条件があります。これが酒税法9条の1項但し書きにあります。
もつぱら自己の営業場において飲用に供する業については、この限りでない。
飲用に共する。・・・・・これは簡単に言いますと、瓶ビールなら栓を抜いてある。缶なら開封してあるってことです。言い方を変えると、開封せずに出す場合は酒類販売許可が必要になります。
じゃあ、スナックで入れたボトルは?
スナックでボトル入れました。余りました。
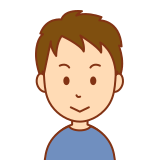
ママさん、持って帰っていい?
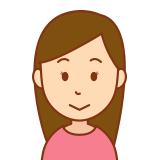
(いやぁーどうしよう)・・・・
ごめんねー持って帰っちゃダメなのよ。また来てねー
という事で、飲み残しを持ち帰ることは酒税法違反となります。
販売
酒類販売の二つの免許
| 酒類卸売業 | 小売業者に販売 | 小売業者に販売ですので自ら小売りは出来ません。 (*飲食店には販売できません) |
| 酒類小売業 | 一般消費者に販売 | 最終消費者に向けて販売(*飲食店、消費者、菓子製造店) |
最終消費者とは:最終消費者は開封する方という理解になります。飲食店は自店で開封するわけですからその段階で最終消費者になります。
この事から、卸売り業は飲食店に販売できません。小売店に売る事しか認められていません。
また、開封する者が最終消費者という建付けですので、飲食店なども小売業から仕入れることになります。
ここで注意点
小売業者は卸業者から仕入れます。少し考えてみてください。クリックで答えが出ます。
×
小売業者は最終消費者に販売しますから小売業者は小売業者に販売できません。
これは簡単に言うと、小売業者から仕入れたものを転売するような小売りは出来ないということになります。
酒類卸業
卸業の8形態
| 全酒類卸売業免許 | 全種類の取り扱い可能 |
| ビール卸売業免許 | ビールの取り扱い可能 |
| 洋酒卸売業免許 | 国産・外国産の洋酒(発泡酒はここ) |
| 輸出入酒類卸売業免許 | 自社で輸出入して卸売できる |
| 店頭販売酒類卸売業免許 | 会員の酒類販売業者への店頭引渡による酒類の卸売 |
| 協同組合員間酒類卸売業免許 | 加入事業協同組合員への酒類の卸売 |
| 自己商標酒類卸売業免許 | 自社開発の商標や銘柄の酒類の卸売 |
| 特殊酒類卸売業免許 | 事業者の特別なニーズへの対応にのみ酒類卸 |
酒類小売業
酒類小売業の3つの形態
| 一般酒類小売業 | 一般的な酒屋さんがイメージしやすい形 |
| 通信販売種類小売業 | 2以上の都道府県に向けて通信販売 店頭での小売りは出来ません |
| 特殊酒類小売業 | 法改正により大部分が一般に統合されこの免許に需要はほぼ無いと思われます。 |
まとめ
これから始めようとする方は一般小売と通信販売が多いのではないでしょうか
若しくは、小売店が、店舗の別スペースで提供する場合です。
その際、仕入れは卸業者から仕入れた酒類ではNGということになります。基本的な形として小売りと提供を併存する場合に同じものを売るにも関わらず、仕入れ先の保有免許が問題になり、仕入れが確実に分離されていることが必要です。
そのあたりの部分に行政書士の出番があるのではないかと思っています。
今回はここまで。ありがとうございました。

